“25年外ブラドライバー一斉計測”して分かった!依然「重心深度>重心距離」傾向が強め/外ブラ1W研究#1
外ブラドライバーの新製品ラッシュで幕を開けた2025年。テーラーメイド、キャロウェイの“常連組”に加えて今年はピンも参戦、コブラも交えて新製品四つ巴の様相を呈している。昨夏に発売されて評価の高いタイトリストの「GT」シリーズも含めて、外ブラドライバーの徹底研究を行った!
テーラーメイド、キャロウェイ、ピン、コブラ、タイトリスト、5メーカーの最新ドライバーについて、ヘッド計測をクラブ設計家でジューシーを主宰する松吉宗之氏、試打を野仲茂プロに依頼した本特集。まずはヘッド計測の基礎知識について松吉氏に説明いただいた。計測項目は下記で、それぞれの数値の見方を教えてもらおう。
●重心距離
40mmくらいが現代の平均値です。38mmを切ると短い、42mmを超えると長いと言えます。今年はそんなに長いモデルはありませんでした。23年、24年のモデルはドローバイアスを付ける狙いで短いモデルも多かったです。
●重心深度
重心距離同様40mmくらいが現代の平均値です。今回登場するモデルは35~45mmくらいですが、驚異的に深いのがピンでした。
●重心高
フェースの高さ(大きさ)がモデルによって けっこう異なるので、下から測った数字を低いと評価していいのかどうか、悩むところではあります。過去においては重心点より上で打ったほうが低スピンになりやすいからそこが飛ぶエリアと考えると、その大きさをどれくらい確保するかが重要と言われていたので、重心高さ2(有効打点距離)を気にしていました。これをどう捉えていくかが今後の問題でしょう。
●ヘッド左右MOI(慣性モーメント)
ヘッド体積に0を一つ付けたくらいの数値が出ていれば、きちんと設計されていると評価できます。例えば、ヘッド体積が300ccだと3000 g・cm2です。現代の大型ヘッド460ccだと4600 g・cm2が標準値で、平均値は4700 g・cm2弱くらいですね。プレーヤーが体感できるのは4300 g・cm2くらいで、物理学の計算上はそれ以上大きな差が出ません。
体感値の差が大きいのが、2000~3000 g・cm2の違いです。3000 g・cm2を超えるとゆるやかに、4300 g・cm2を超えるとじりじりと上がっていくので(2次曲線で表される)、体感するのは難しい。左右だけでなく上下のMOIもあるのですが、こちらはあまり体感できません。ピンの「G440 MAX」のように5000 g・cm2あるがゆえにできることもあるのですが、ここまでなくても性能的には大丈夫です。
●重心角
つかまりに影響する数値です。長年測ってきた感じだと、25度くらいが平均値です。小さいと20度、大きいと30度くらいのモデルもあります。重心距離40mmで重心角23度くらいのモデルはバランスがいいと思います。
●FP値(フェースプログレッション)
平均値はだいたい18㎜くらいです。以前はもう少し大きかったのですが、減少傾向にあると言えます。10年位前は19~20㎜くらいありました。14㎜台になると小さいと言え、外ブラモデルは総じて小さい傾向です。
●ヘッド体積
チタンの300ccの時代から技術革新によりヘッドを大きくしていった時代、ヘッド体積は重要視されていました。しかしルールで460ccと決まった現代では、この数字はあまり意味をなさないと思います。現代の技術では厚みや凹凸の付け方で体積はいくらでも調整可能です。体感的には投影面積のほうが重要ですが、数値化は難しい。ちなみにルールでは460ccが上限と定められていますが、測定誤差プラス10ccが認められており、実質的な上限は470ccです。
“やさしいドライバー”ってどういうこと?
計測数値を読むうえで、最近のゴルフクラブの「やさしさ」について理解しておくほうがいいと思います。「MOIが大きいと曲がらない」と思われがちですが、大MOIヘッドを使っても曲がる人はたくさんいます。その理由は、インパクトでフェースが真っすぐ向いていないからです。
「フェースを真っすぐ向けて打たせる」ことがクラブ作りのポイントであり、各メーカーは研究を重ねています。この点コブラが上手ですね。フェースを真っすぐ向けて打たせるには、2つの方法があります。
<その1>自分でつかまえやすい
自分でつかまえやすいクラブとは、重心距離が短めでフェース向きをコントロールしやすいクラブのこと。これが必要な人は2通りいます。一つはフェースコントロールが上手でそれを駆使している人。もう一つは正しいスイングができないため開いて当たりそうなのをなんとか真っすぐ当てている人です。上手い人とそうでない人は別のものを使わなければいけない印象が強いですが、実はそうではないんです。右に行く人がつかまるクラブで上手くいく場合と、それでも右に行く人がいる。こういう人に対応するために、メーカーは性能の異なるモデル(下記、つかまえてくれるクラブ)を同時に開発しているんです。
<その2>クラブがつかまえてくれる
重心距離と重心アングルのバランスなどで、誰が打っても、真っすぐ、右、左に行きやすいクラブがあります。正しいスイングができずスライスに悩んでいる人には、誰が打っても左に行きやすいモデル(近年「ドローバイアスモデル」と呼ばれる)が合います。こういうクラブを「やさしい」と表現することが多いです。ここ2~3年のトレンドはやさしいモデル。クラブがつかまえてくれるから、正しいスイングができる人にとっては左に行くモデルばかり…。ですので、ツアープレーヤーたちはドローバイアスをシャフトで抑えて使っています。その証左として、ツアーではあまり動かないシャフトが流行っていますよね。
誰が打っても真っすぐ!? 「G410 PLUS」の大ヒット
「誰が打っても真っすぐいくクラブ」がヒット商品になります。上手い人も使えるからです。正しいスイングができたときに真っすぐ飛ぶので、道具に助けてもらわないとスライスする人にとってはやさしくありません。
近年で言うと、ピンの「G410 PLUS」が爆発的にヒットした理由は、「誰が打っても真っすぐ」のバランスが取れている、大MOIクラブだったからです。ヘッドスピードに関係なく、動きが正しい人のバラつきをクラブが(大きなMOIにより)補正してくれるので、トッププレーヤーも一般アマチュアも使えました。「デカいの苦手だったけど打てちゃった」という人も少なくなかった。このドライバーはゴルフ界のひとつのベンチマークになったと言えるでしょう。「慣性モーメントが大きくても多くのトッププレーヤーが使っている!」 と言われましたが、その理由は本質的にはヘッドのバランスにあったのです。
ただし、スイングが正しくない人はこのクラブでは真っすぐ打てません。「G410 PLUS」で打てなかった人をどう取り込むかが、ピンを含む多くのメーカーにとっての開発課題となったのです。大型ヘッドで育った若いプロは大MOIでいいけれど、フェースコントロールをしたいプロもまだまだ多く、重心距離があまり長くないほうが扱いやすいと感じます。こういう人たちへ向けてアジャストされたモデルが、「G410 PLUS」以降にいろいろ出てきて、性能的には行ったり来たりを繰り返してきました。
ヘッドのパーツで重いのはネックとフェースで、これらに対して後ろにウエートを配置するとMOIがアップします。ウエートが後ろにあると重心深度が深くなってスピン量が増えるなど弊害も生じてきます。こうなると他でスピンを減らす工夫が要るのと、インパクトで合わせていくプレーヤーにとっては挙動が鈍いので合わせにくくなる。タイトリストはこれを分かっているので、MOIをあまり大きくしません。設計がブレていないですね。
重心深度と重心距離の関係が重要
以上のことを踏まえると、クラブの振った印象を決めるのは、重心深度と重心距離の数値のバランスだと思います。2つの数字が近い(差が1~1.5mm程度)と、ヘッドから感じるヘッドの印象は普通。重心深度のほうが大きいと、やさしいしつかまってくれる。逆に重心深度のほうが浅いと、つかまらない、すべる、ちょっと難しい…という印象になると思います。大前提として、それぞれの数値の大小が顕著であれば、その数字を重視して性能を判断します。(取材・構成/中島俊介)
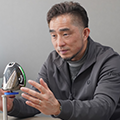
松吉宗之(まつよし むねゆき) プロフィール
ジューシー株式会社の代表取締役。ゴルフクラブメーカーにて、クラブの設計開発に20年以上携わる。2018年にジューシー株式会社を設立。自社製品だけでなく、OEMでの設計も行う。3D CADを用いたデジタル設計をいち早く導入し、数値に裏付けられた革新的な性能のクラブを多数開発。その傍ら、膨大な数のクラブヘッドを自身で測定し、ゴルフクラブの性能や製法の進化を独自に研究し続けている。







































